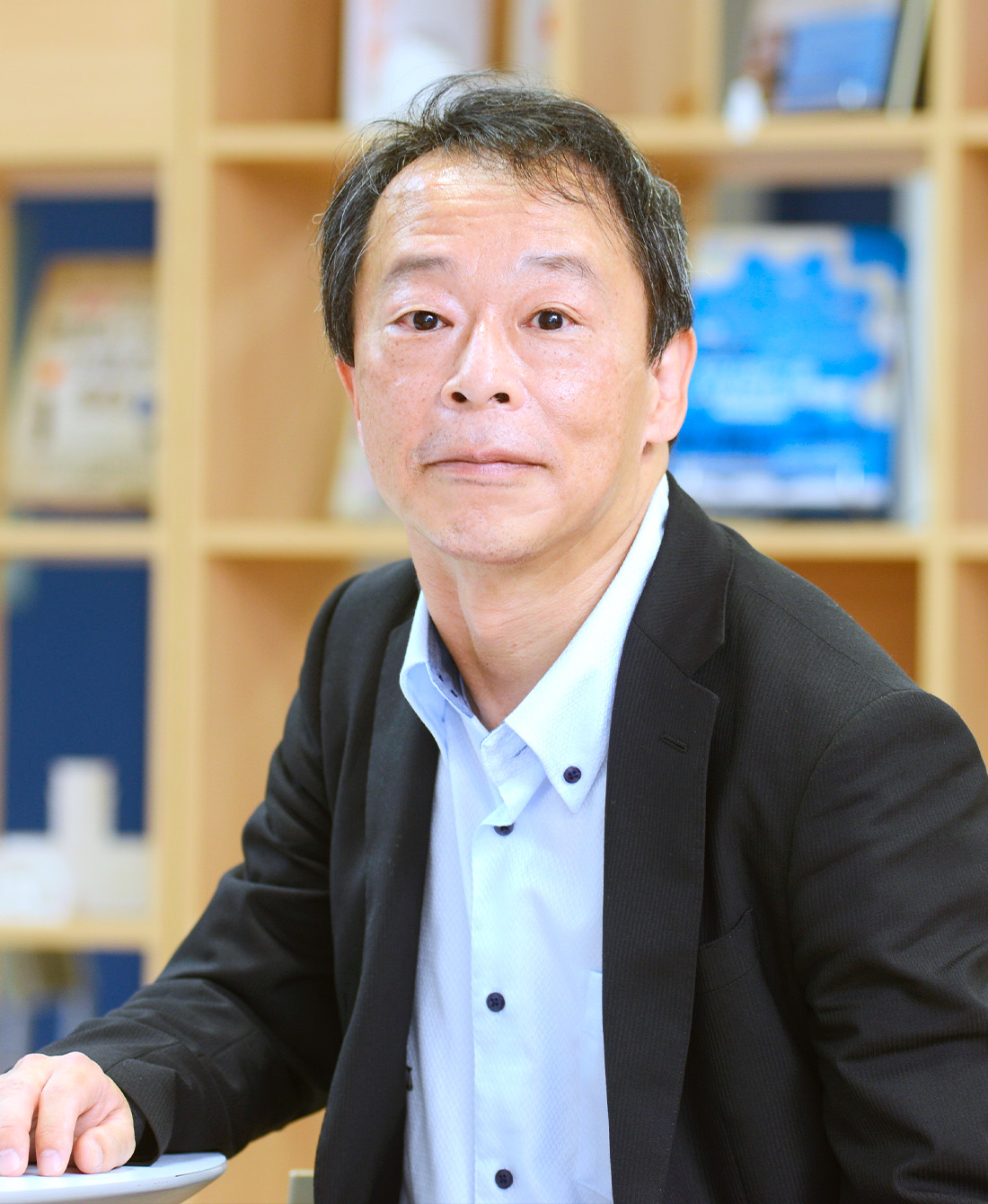INTERVIEW
インタビュー
ソーシャル・データサイエンス学部・研究科の魅力
現代は、様々な大量のデータが入手可能で、こうしたデータをいかに活用するかが、ビジネスや社会において重要です。こうしたデータから有益な情報を抽出する方法を開発し応用するのがデータサイエンスです。ただ、データサイエンスを使って現代のビジネスや社会における様々な課題を解決するためには、データサイエンスの技術を学ぶだけでは十分ではありません。経済学、経営学、マーケティング、法学、社会学など社会科学の知識も必要になります。本学部・研究科の魅力は、データサイエンスの技術に加えて、社会科学も体系的に勉強できることです。その上で、ビジネス・イノベーション科目、社会課題解決科目、PBL演習、ゼミなどで、社会科学とデータサイエンスを融合させて、ビジネスや社会の課題を解決する方法を実践的に学べることも、本学部・研究科の魅力です。
ソーシャル・データサイエンス学部・研究科で進めたい教育・研究
教育面では、学部で「ファイナンスとデータサイエンス」、「金融市場データ分析」、修士で「高頻度資産価格データ分析」とファイナンス関係の授業を担当します。「ファイナンスとデータサイエンス」では、ファイナンスの基礎理論と実証分析について講義を行います。「金融市場データ分析」では、時系列分析を用いて、資産価格が日々どのように変動しているかを分析する方法について講義し、実際の株価データを用いた演習を行います。「高頻度資産価格データ分析」では、資産価格の日中の高頻度データの分析について、講義と演習を行います。研究面では、資産価格の日中の高頻度データを用いて、ボラティリティ変動を表す時系列モデルを開発し、金融リスク管理に応用すると共に、マクロ計量モデルの拡張と景気循環への応用も行います。計量手法として、これまで、主にベイズ推定法を用いてきましたが、今後は機械学習も取り入れて行きたいと思います。
■学部ゼミナール紹介
私の学部ゼミナールでは、主として、ファイナンスやマクロ経済学の計量分析を扱います。このテーマについて学ぶためは、統計、数学、プログラミングに加えて、ファイナンスやマクロ経済学の知識が必要になります。そのため、私の学部ゼミナールを志望する方は、学部1・2年次に、必修科目以外に、「社会科学入門(金融)」「社会科学入門(経済学)」「ファイナンスとDS」「マクロ経済学とDS」を履修することをお薦めします。分析手法として、頻度論統計学に加え、ベイズ統計学を使いますので、「ベイズ統計学Ⅰ」も履修しておくとよいと思います。
■学部ゼミナール紹介
私の学部ゼミナールでは、主として、ファイナンスやマクロ経済学の計量分析を扱います。このテーマについて学ぶためは、統計、数学、プログラミングに加えて、ファイナンスやマクロ経済学の知識が必要になります。そのため、私の学部ゼミナールを志望する方は、学部1・2年次に、必修科目以外に、「社会科学入門(金融)」「社会科学入門(経済学)」「ファイナンスとDS」「マクロ経済学とDS」を履修することをお薦めします。分析手法として、頻度論統計学に加え、ベイズ統計学を使いますので、「ベイズ統計学Ⅰ」も履修しておくとよいと思います。
CLASS
担当授業科目
- ファイナンスとデータサイエンス
- 金融市場データ分析
- PBL演習C
- (院)高頻度資産価格データ分析
- (院)リサーチ・ワークショップⅠ・Ⅱ
RESEARCH
研究内容
私は、計量ファイナンス、マクロ計量経済学、ベイズ計量経済学の分野で研究を行っています。計量ファイナンスでは、主に、資産価格変化率の分散もしくは標準偏差を表すボラティリティについて研究しています。具体的には、資産価格の日次データや日中の高頻度データを用いて、日次あるいは日中のボラティリティ変動を表す時系列モデルを開発し、金融機関が行っている、将来のボラティリティの予測、オプション価格の導出、バリュー・アット・リスクや期待ショートフォールといった分布の裾のリスクの予測などに応用しています。マクロ計量経済学では、DSGEモデルと呼ばれるマクロ理論モデル、VARモデルと呼ばれるマクロ時系列モデルの拡張を行っています。また、マルコフ・スイッチングモデルの拡張と景気循環への応用も行っています。ベイズ計量経済学では、上記のモデルを推定するために、マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を用いたベイズ推定法の開発を行っています。
キーワード
- 金融リスク管理
- 景気循環
- 高頻度データ
- ベイズ統計学
- ボラティリティ
- マルコフ・スイッチング
- DSGE
- MCMC
- VAR